1.“いい音”には”いい響き”が必要
ハーモニカを吹いていて、
「あ、今の音、いい音だな、なんか気持ちいいな」と感じたことはありませんか?
その感覚って、ただ音程が合ってるとか、リズムが揃ってるだけじゃなくて、
響き方”がしっくりきてるからだと思うんです。
僕自身、長くハーモニカを吹いていく中で、
音が太くなったり、柔らかくなったり、深くなったりする瞬間って、
すべて「口の中の響き」が関係しているんじゃないかと思うようになりました。
ただ音を出しているんではなくて
“響かせている”。
そう感じるんです。
そしてある時、
その“響き”にちゃんと名前があることを知りました。
それが――
「フォルマント」という言葉です。
2.フォルマントって、どんなもの?
フォルマントというのは、
もともと音声学や音響の分野で使われている言葉で、
「音の中で特に強く共鳴する周波数帯」のことを指します。
たとえば、人の声。
「あ」と「い」は声の高さが同じでも、
口の中の形が違うことで、まったく別の音に聴こえますよね。
それは、響きが変わっているからです。
この響きの違いこそが「フォルマントの違い」なんです。
声は、声帯で作られた音(基音)に倍音が重なり、
その中のどこが強く響くか――
つまり、どの周波数帯と“ピントが合う”かで、音色や個性が生まれます。
この「共鳴のクセ」がフォルマント。
そして、それをコントロールしているのが、
舌の位置や口の容積、喉の開き方といった、口の中の状態です。
つまり、フォルマントは「意識して動かせる」んです。
そしてこれは、人の声だけじゃなく――
ハーモニカでも、まったく同じことが起きているんです。
3.ハーモニカとフォルマントの深い関係
僕はベンドの解説をするとき、
いつもこう言っています。
ベンドを習得するには、二つ大事なことがあります。
ひとつは、「息が漏れずにしっかり音が出せること」。
そしてもうひとつが、
「口の中の響きを変えられること」。
この“響きを変える力”こそが、まさにフォルマントを動かす力なんです。
たとえば、ベンドでは、
舌を少し引いたり、喉を詰めたりすると、音が少しずつ下がっていきます。(音によって動かす場所、度合いは変わります。)
これは、口の中の響きが変わることで、
リードの振動が変化して、別の音が導かれる現象です。
つまり、ベンドは息だけでなく、響き=フォルマントでもコントロールしている。
この感覚が安定してくると、音程だけでなく、
音色まで変えられるようになります。
だから、グッとくる演奏をする人の音って、「ただ音が鳴ってる」のではなく、まるで“歌っている”ように聴こえる。
それはきっと、音の高さだけでなく、響き(=フォルマント)を丁寧に合わせているからだと思います。
ハーモニカを“声”のように響かせるためには、
このフォルマントという視点が、実はすごく大切なんです。
4.モノマネ芸人とホーミーの話
フォルマントって聞くと、
ちょっと難しそうに感じるかもしれません。
でも、実はすごく身近なものなんです。
たとえば、モノマネ芸人さん。
彼らが人の声を真似するとき、
ただ声の高さを変えているわけじゃありません。
「その人らしい響き方」まで真似してるんですよね。
つまり、フォルマントを真似してるんです。
声の高さは同じでも、響きが変われば、声の“質感”はガラッと変わります。
その響きを操るのが、まさにフォルマント。
僕は前から、よくこう言ってました。
「モノマネ芸人さんは絶対ベンドがうまいはず」(^)3^)。
そしてもうひとつの例が、ホーミー(喉歌)。
モンゴルなどで歌われている伝統的な歌唱法で、
ひとりで低音と高音を同時に鳴らす技術です。
この高音は、声帯が出しているわけではなくて、
フォルマントを極端に尖らせることで、倍音の一部だけを強調して鳴らしているんです。
まさに、フォルマントを“意識して動かす”技の極致。
響きを変えることで、音の印象が変わる。
これは、ハーモニカにもそのまま当てはまります。
「音を出す」のではなく、
「響かせて鳴らす」という感覚。
それが、フォルマントの世界なんです。
↓↓↓ちなみに、ホーミーを自在に操る、大好きなバンド、フスグトゥン。すごすぎです。

5.響きを吹くということ 〜フォルマントを見つけろ。〜
ハーモニカを演奏していて、
「この音、なんか出にくいな…」って思うこと、ありませんか?
高音が細くなったり、低音が詰まったり。
それって、もしかすると、
その音に合ったフォルマントがまだ“合ってない”だけなのかもしれません。
フォルマントというのは、
すべてのハーモニカ奏者にとって大事なものです。
音色にも、ベンドにも、ビブラートにも、
ハーモニカの“声”をつくる多くの表現に関わっています。
でもこれは、誰かに「こうすればいい」と教えてもらうというよりも、
自分の中で「しっくりくる」響きを探していくことが何より大事なんです。
たとえば、同じ音でも、
舌の位置を少し変える、喉を広げる、口を少しすぼめる。
そうやって吹いてみると――
「あ、今、音が気持ちよく鳴った」
そんな瞬間があるはずです。
そのときの感覚は、まさに
「音にピントが合った」ようなもの。
今まで少しぼやけていた音が、
急にクッキリ、深く、響きを持って鳴り出す。
それが、フォルマントが“その音に合った場所”にピタッと重なった状態です。
音が鳴りにくいときというのは、
フォルマントと音の“相性”がまだ合っていないだけかもしれません。
つまり、音を出すというより――
その音にフォルマントを合わせる。
この「響きにピントを合わせる」感覚が、
ハーモニカの演奏をもっと自由に、もっと自分らしくしてくれるはずです。
フォルマントが合ってくると、
今まで何気なく吹いていた音が、
自分の声みたいに感じられてくると思います。
だから、これからはこの言葉を合言葉にしませんか?
“フォルマントを見つけろ。”
音を出すだけじゃなく、
響きを感じて吹くこと。
それが、ハーモニカが“自分の楽器”になった瞬間なんだと思います。
(^)3^)♫

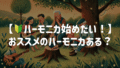
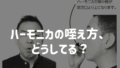
コメント